受精卵凍結保存「ガラス化法の原理」とは?
凍結保存した受精卵を使わないで体外受精治療を卒業する方は、とても少ないと思います。
日本では、体外受精で生まれる赤ちゃんの90%以上が凍結した受精卵から生まれています。
では受精卵は、実際どのような方法で凍結されているのでしょう?
受精卵を凍結する際は水分を抜く必要があります
細胞を凍結させるときに最も頭が痛い問題は、細胞内の水分が凍って氷になり、大切な器官を傷つけてしまったりすることです。
図1:水道管破裂
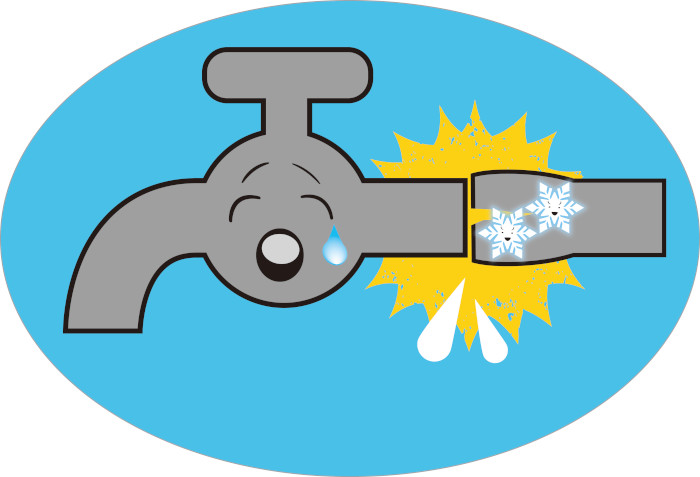
水が凍って氷になると、体積が増します(水の約1.1倍の体積となります)ね。
この現象は、冬に凍結して水道管が破裂したり(図1)、氷が水に浮く(氷の方が水より軽い)ことからもわかります。
何も準備をせずに水をたくさん含んだ細胞を凍らせると、細胞の中の水分は氷となって体積を増します。
そして水道管が破裂するように細胞膜が破れてパンクしたり、ミトコンドリアや核と言った細胞の中の大事な器官(小器官とよんでいます)が氷の結晶で傷ついたりします(図2)。
図2:細胞内氷晶形成
.jpg)
そこであらかじめ水を抜いておき、細胞の中で氷ができにくくする必要があることは、精子の凍結保存のコラムでお話しました(コラム「精子の凍結保存」)。
参考記事:精子の凍結保存〜凍結しても大丈夫?〜
水分を抜きすぎても細胞が弱ってしまいます
ところがその一方で、水をあまり抜きすぎると細胞は弱ってしまい、十分な仕事ができなくなります。
特に受精卵のように、別々の部署で決められたスケジュールで次々と新しい仕事をしていく細胞では、スケジュールに乱れが発生すると細胞の発生が止まってしまうことがあります。
自動車製造などのいくつも工程のある工場で、いくつかの部署でトラブルが起こると工場全体が停止してしまうようなものですね。
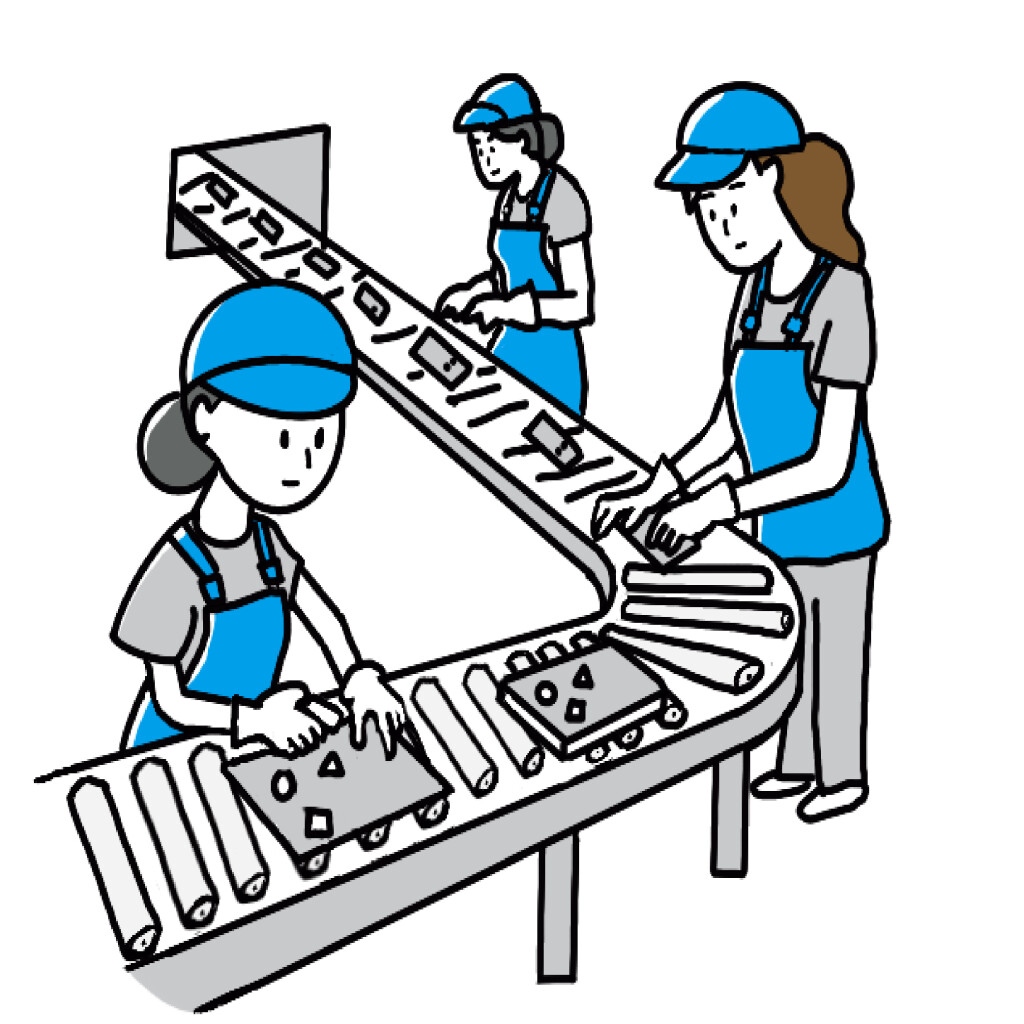
そこで、フル稼働で動いている細胞の仕事を瞬間的に止めて凍結し、溶かした後もすぐにフル稼働でもとの仕事に戻れるように、必要な水を残しておく必要があります。
ところがこの水は、うまく凍らせないと体積が増して危険な氷の結晶を作ります。
結晶を少なくするために水は減らしたい、でも必要な水は十分残したい、難しいジレンマです。
そこで最低限必要な水を残し、これを「体積があまり変わらない」「氷の結晶ができにくい」ように受精卵をうまく凍結できる方法が開発されました。
一般に「ガラス化法」と呼ばれているこの方法では、三段階で凍結の準備をします。
受精卵を凍結する「ガラス化法」の手順
ステップ1:細胞に物質を染み込ませる
第一段階では、細胞にDMSOやエチレングリコールという物質を十分しみこませます(図3、b)。
自動車が好きな方はご存じだと思いますが、エチレングリコールはエンジンの冷却水に混ぜる不凍液の成分で、これらの物質は温度が下がったときに水が結晶になるのを防ぎます。
ステップ2:細胞から水を抜く
第二段階は、細胞から水を抜く操作です。
このときには、細胞の外側の溶液にDMSO・エチレングリコールにくわえて、非常に濃いショ糖(スクロース/sucrose)等の糖を混ぜて、ちょうど塩でナメクジを小さくしてしまうように、細胞から水を引き出します。
第二段階が終わった時点で、水が抜けて小さくなった細胞の中には濃度が高くなったDMSO・エチレングリコールがあって氷の結晶がさらにできにくくなっています(図3,c)。
図3:ガラス化保存の原理
.jpg)
ステップ3:細胞を凍結する
第三段階はいよいよ凍結です。
ここでは細胞をいれた容器を思い切って-196℃の液体窒素にジャボン、と一瞬で浸します。
乱暴に聞こえるかもしれませんが、温度が下がるスピードが早いほうが結晶はできにくく、グズグズしているとかえって結晶ができて細胞にダメージがあるのです。
DMSOやエチレングリコール等の成分の働きと、冷却する速度を極限まで速くすることで、細胞の中の水はそのままの形で固体になり、体積の変化がほとんど起こりません(図3,d)。
つまり「氷にならず水のまま固体になる」のです。
凍結した受精卵を溶かす方法
凍った受精卵を溶かすときには、凍らせたときと同様に急速にあたためて水に戻してから、DMSOやエチレングリコールを急いで細胞から洗い出します。
こうして、細胞は結晶で弱ることなく、それまでの複雑な仕事を滞りなく、続けることができるのです。
「氷にならずに固体になる」ってどういうこと?
たしか小学校で「水は温度を上げると気体(水蒸気)になり、温度を下げると氷(固体)になる」と習いました。
その通りなのですが、水は普通に凍って「氷」になる以外に、特にDMSOやエチレングリコールを含んだ状態では「ガラス化」という別の状態で固体になることができるのです。
そのため、この凍結法をガラス化法、と呼んでいます。
この状態では水はそのままの形で分子が止まってしまうので体積が増えたり減ったりしませんし、結晶ができないために周りの構造に傷をつけることもありません。※
※水の分子は動き回っていますが、0度以下になり「氷」になると結晶化し動かなくなります。整然と結晶化することで体積が増えます。
ですが「ガラス化」は結晶化せず水のままで動きが止まるので体積が増えないということです。
「ガラス化」した状態は普通のガラスより不安定
ただ、受精卵を凍らせるときの細胞内のガラス状態の水は、普通のガラスほど安定ではありません。
ガラス状態を作るために加えるDMSOやエチレングリコールも、高い濃度で長時間細胞に触れると細胞を弱らせます。
ですので、ステップ2(第二段階)で水を受精卵から出すときの時間は(高濃度のDMSOやエチレングリコールの毒性を減らすために)30秒と必要最低限に抑えられています。
またステップ3(第三段階)で溶液を凍らせる速度を増してガラス状態を安定させるために、受精卵を浮かしている培養液の量を極限まで抑えるなど、様々な細かい注意が払われています。
豆知識:ガラスの特性や歴史あれこれ
ガラス化法の名前のもととなっているガラスは、主にケイ酸(シリカ)を含む混合物を高温で溶かしてからまた冷やしたものです。
ガラスは溶かせば様々な形に加工することができるので、窓ガラスや、ワイングラス、あるいは眼鏡など、私たちの身の回りでたくさん使われていますね。
工房でグラスや、風鈴を作った方はお気づきだと思いますが、真っ赤に焼けたドロドロの状態から温度が下がって透明になるまでガラスはほとんど体積が変化しません。
そのため、焼き物の様に、温度が下がったあとで割れてしまったり、ひびが入ると言うことが少なく、複雑な形に加工することができるのです。
体積が変わらない理由は、ガラスの中でケイ酸の分子が細胞の中のガラス状態の溶液と似たように不規則に配置していて、結晶の水晶のように整然と並んでいないからだと考えられています。
歴史のなかのガラス
加工されたガラスは、とても安定しています。
そのため非常に昔のガラスが様々なところから発見されます。
ガラスの原料がどこで採掘され、どこで加工されて輸出されていたか、道筋をたどれば古代の交易の様子がわかるかもしれないために、古代ガラスの化学分析は数多くの研究者を魅了してきました。(1)
ガラスを含む工芸品はBC2000年頃からシリア(メソポタミア)、エジプト、ギリシャで見つかっています。
1982年に、トルコ南部のウルブルン半島沖でBC1300年ころ(同位体などの測定でかなり正確に分かっています)の難破船が見つかり、青銅の原料となるスズや鉛の塊などとともに、加工する前の美しい青ガラスの塊が多数見つかりました。
このガラスの塊の化学分析から、この頃には40kgを超す非常に均質なガラスを一度に製造する技術がエジプトにあったことや、メソポタミアとエジプトはお互いにガラスの原料をやりとりしていた可能性があることがわかりました。(2)
図4:ガラスの交易
.jpg)
引き上げられた位置から、船はキプロスあるいはレバノンあたりからエーゲ海方面、もしかすると南部ギリシャのミケーネに向かっていたのではと推測されています。
日本では竪穴住居で底のとがった縄文土器に木の実を貯めて保存食とし、魚や獣を捕って人々が暮らしていた頃、地中海ではファラオの工房で質の高いガラスが大量に作られて、ギリシャの将軍たちが恋人に贈る装飾品を作るために輸出されていたのかもしれません(図4)。
(1) Carolyn Wilke. A Brief Scientific History of Glass. Smithsonian Magazine November 24, 2021
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/a-brief-scientific-history-of-glass-180979117/
(2) Lankton JW., Pulak C., Gratuze B. Glass ingots from the Uluburun shipwreck: Glass by the batch in the Late Bronze Age. J Archaeol Sci 2022;42: 103354